001 太陽系の秘密
真・創世記
-宇宙人が明かす太陽系の秘密
(徳間書店から出版した「宇宙人がくれた21世紀の聖書」から、Thomaが現実の歴史と比較した部分を抜粋して提供します。セムヤーゼの言葉を青にしてあります。黒がThomaの調査記録です。)
マイヤは宇宙人によって、太古の多くの預言者と同様に、「真理の伝達者」として選ばれた。
(中略)
本章では、宇宙人セムヤーゼたちが最初のコンタクト以来、マイヤに与えてくれた天文学的な知識を中心に、旧約聖書の「創世記」にも比すべき壮大な宇宙の歴史を見ていこう。
ノアの洪水は一万七九年前に起こった旧約聖書に有名な天変地異「ノアの大洪水」はいつ起こったのだろうか。
このテーマは多くの歴史学者、考古学者、聖書学者によって追求されてきた。
洪水伝説は世界中に、いろいろな民族の間に数多く残されているが、それぞれに、その起こった時期を特定することはむずかしい。
あるいはすべての伝説が、ある一つの大洪水の記憶を別々な形で伝えているのだろうか。
「ノアの洪水」だけは、聖書にノア六百歳のときと、時期がわかっている。
聖書によって人類の歴史を遡ると、アダム誕生はいまから六〇〇〇年ほど前のころである。
創世記第五章のアダムからノアまで、第十一章でセムからアブラハムまで、そして新約聖書でアブラハムからイエス誕生まで、彼らが生きた年代を加算し、西暦を加算する。
マイヤがセムヤーゼと初めて会見した一九七五年を中心に考えると、ノア六百歳のときは四〇九三年前である。
ノアの洪水に関するセムヤーゼの説明を聞こう。
====
セムヤーゼ
それでは人類の歴史についてお話しします。
あなたがた地球人の時間計算は正確ではありません。事実を中途半端に計算しています。
あなたがたの科学者や研究者の誤差は数千年以上にもなります。
地球の多くの研究者は、昔から聖書に述べられている有名なノアの洪水の正確な年代について計算しようと努力してきました。
しかし、現在まで見るべき成果はあげていません。
あなたがたの今日のキリスト教的時間に換算すると、ノアの洪水は(一九七五年の)一万七九年前に起こったのです。
一個の巨大な彗星が地球を軌道から追いだし、地球の公転軌道と周期を変えてしまったのです。
その結果、地球に大惨事が起こったのです。
その当時地球の一日は四〇時間以上にもなり、今日のように太陽は東から昇りませんでした。
大洪水の後、公転周期と軌道の変化は二度地球を襲いました。
しかし、この大洪水のような壊滅的大惨事は起こらなかったのです。
最後の大転覆は三五〇〇年前に起こりましたが、それについては後にお話しします。
一万七九年前に起こった大洪水は、一個の巨大彗星によって引き起こされたものであり、地球に測り知れない損害をもたらしました。
この巨大彗星は、太古の昔から宇宙を移動しつづけていたのです。
私たちはこの彗星を「破壊者」と呼んでいます。
そして私たちは、この破壊者が百万年前から宇宙空間を、猛り狂いながら飛行していたことを知っています。
あなたがたの時間尺度に従えば、この危険な彗星の公転周期は五七五年と二分の一であり、西暦二二五五年に再び地球の勢力圏に達し、きわめて危険な状態に陥るでしょう。
ただし、何らかの宇宙的事情で破壊者の軌道に異変が起こらないこと、あるいは破壊者が崩壊されないことという条件つきですが。
破壊者の前回の通過は二九五年前、つまり一六八〇年に起こりました。
====
「ノアの洪水」の時期についてはいろいろ研究されており、メソポタミアの古代の町の王であったギルガメシュの洪水記録と聖書の記述が似ていることから、聖書のほうはそれを借用したものとする意見がある。
洪水伝説のあった場所などのボーリングによる地質調査では、西暦前三五〇〇年とか二八〇〇年に洪水があったと報告されているが、一万七九年前の時期の特定をする資料はない。
仮に、セムヤーゼの言うように一万七九年前が事実だとすれば、聖書による人類の歴史は大きく変わってくる。
古代の歴史家や伝説が伝えている古い歴史はたくさんある。
紀元前四万九〇〇〇年以上前にはじまるエジプト年代記や紀元前一万八六〇〇年以上前にはじまるマヤの年代記などがあり、真実はまだ明らかになってはいない。
大彗星「破壊者」の徘徊
セムヤーゼは、洪水を引き起こしたのは巨大な彗星であったと語り、それを「破壊者」と呼んだ。
近年の地球科学の進歩は、過去何回も、彗星の大接近や巨大限石の衝突が地球に対してあったことを明らかにしている。
そのたびごとに地球の気候は大変動し、生物は絶滅、進化を繰り返した。氷河期のはじまる直接的な原因を、接近した彗星からふりそそぐ流星塵に求める説もある。
六五〇〇万年前、中世代の末期に恐龍が絶滅した気候変動の原因も、最近では巨大限石の衝突だとする説が有力になった。
その証拠としてあげられたのは、ヨーロッパで、恐龍か滅んだとみられる時代の地層から、イリジウムというめずらしい元素を異常に多く含んだ粘士屑が発見方れたということである。
古生代の末期、紡錘虫(フズリナ)がいくつもの類に分化したのち、そろって絶滅していることから、この時期に全地球的規模の大災変を想定したのはフランスの古生物学者キュビエだが、このときも巨大限石の衝突があったのかもしれない。
宇宙人セムヤーゼが言うように、地球上の大災変の原因が彗星にあったということは意味をもっている。
すなわち、地球は宇宙のなかで孤立しているのではなくて、宇宙に対して開かれた系であり、異なる天体どうしの接近によって一大ドラマが展開してきたのである。
彗星は古代の人々には悪い出来事の前兆と考えられていたようだ。
天変地異と災厄を結びつけて考えた根底に、伝説として残された遠い記憶があるからのようだ。
旧約聖書のヨシュア記第一〇章に、ヨシュアが主に願って、日と月をまる一日静止させたとある。
ヴェリコフスキーは自著「衝突する宇宙」のなかで、世界各地に伝わる同様な伝説を分析し、これは地球が彗星の尾の中に入った事件だったと推理している。
そのために地球は自転にブレーキがかかり、日と月は動かなかったというのが事実であろう。
ともあれ、過去何回もの彗星の接近による大異変が、地球の進化に関係してきたという見解は、近年多くの科学者によって支持されている。
「破壊者」はホイストン彗星か
セムヤーゼは、ノアの洪水を引き起こした彗星の公転周期は五七五年と二分の一であり、最後に地球を通過したのは一六八〇年であったと語った。
これまで出現が記録されている彗星の数は約一八〇〇個で、一九八一年まで七一〇個の彗星は軌道が計算されている。
そのうち、一二一個は周期が二〇〇年以内の周期彗星であり、残りの二八九個は長周期の楕円、三一六個は抛物線、一〇四個は双曲線軌道で、二〇〇年以上の長周期になっているのである。
つまり約六〇〇個が二〇〇年を超える長周期で、なかには一九七三年に地球に接近したコホノテク彗星のように、あと百万年たたないと戻ってこないというものもあるのだ。
だが「破壊者」はそのなかのどれなのか。
一六八〇年に接近した周期五七五年二分の一の彗星-筆者が東京天文台に問い合わせたところ、「本大文台には記録がない」といわれた。
しかしフランスの天文台には、これとピッタリの彗星の記録が残っている。
その彗星は一六八〇年にウィリアム・ホイストンが発見したのでホイストン彗星と名づけられており、周期は五七五・五年で西暦二二五五年に再び地球の近くに戻ってくると予想されている。
この彗星の観測記録はたった一回で、詳しい記録がないのでセムヤーゼのいう彗星と同一のものであると断定はできないが、それである確率は高い。
月を連れてきた巨大彗星の起源
セムヤーゼはノアの洪水の、正確な年代につづいて、それを引き起こした彗星の起源と遍歴について語り、地球の月が最初から地球の衛星として誕生したものではないことを
説明している。
====
セムヤーゼ
地球にとって宿命的なこの彗星と、月の起源の歴史をお話しします。
この彗星が、あなたがたの地球の衛星である「月」を持ちこんだのです。
この月はある遠い太陽系の小さな惑星の断片なのです。
地球の月は、その年齢が地球より四五〇万年古い小惑星に由来します。
まずこの彗星の起源の歴史について述べます。この事件は百万年前に起こりました。
未知の宇宙空間の奥深く、銀河系付近のある太陽系の中で、一つの孤独な惑星が浮遊していました。
この惑星は、太陽の周りを公転する諸惑星の通常の軌道から遠く離れた位置で公転していました。
これは暗黒惑星であり、そこには生命は一切存在しませんでした。
その軌道は危険で不安定でした。
というのも、この惑星は、元所属していた太陽が大爆発を起こし、その結果、その太陽系から放り出されたのです。
つまり、元の太陽の恐るべき大爆発によって、一部の惑星が破壊されたとき、この惑星は危険な弾丸のように暗黒の宇宙に放り出されたのです。
この太陽は自己崩壊しましたが、そのとき、宇宙空間に穴ができました。
この太陽の物質は巨大な力のために自ら圧縮して、小さな固まりになりました。
その太陽は通常の状態で直径が一一〇〇万キロメートルあったのが、縮小したときはわずかに四・二キロメートルになっていたのです。
こうして圧縮された物質はわずか一立方センチメートルの重さが、数千トン以上にもなりました。
それ以来、それはぽっかり口を開けた暗黒の穴として、宇宙に漂うことになりました。
そして、それはその周囲一〇〇キロメートル四方にやってくるすべてのものを恐るべき力で捕え、呑み込んでしまうのです。
===
ここでちょっと、宇宙人の使う「太陽系」という概念に、われわれからすると二つのものが含まれていることを心得ておく必要がある。
セムヤーゼは「太陽系とは、大きな天体が小さな天体を周囲に集めて回転させているとき、そのようなものが太陽系と呼ばれます」という。
衛星を持つ持たないにかかわらず、地球科学のいう惑星をも「太陽系」と呼んでいる。
そして、そのような太陽系(惑星系)が回る中心は特別な名前のついた太陽(恒星)であって、この全体も太陽系(恒星系)と呼んでいるので、混同しないように、必要な場合には、筆者はこれからセムヤーゼの説明を引用するときに適宜、カッコのなかに注を入れよう。
私たちの太陽系全体をセムヤーゼは「ゾル太陽系」と呼ぶ。
宇宙人の説明によると問題の彗星はある恒星系に属していた惑星だったが、その恒星が爆発して自己崩壊したときに、それはその太陽系から放り出されて放浪の旅に出たという。
また、その恒星の末路は中性子星となり、何ものをも引き込んだブラックホールになったことが推察される。
放浪惑星が
ある太陽系に引き起こした惨事
セムヤーゼはこの彗星が地球にどこからか月を連れてきたのだと述べている。そのことはのちに説明されるが、それに先立ってこの放浪惑星(彗星)がわれわれの太陽系(ソル太陽系)につかまる前に大惨事を引き起こした、ある太陽系の歴史が語られる。
月はその太陽系から、はるか宇宙空間を越え、放浪惑星に伴われてわれわれの太陽系まで飛来したのだという。
===
セムヤーゼ
当時この太陽(注・第一の恒星系)によって投げ飛ばされた暗黒惑星は、再び近くの太陽系(注・第二の恒星系)に捕獲され、その周りを不安定な軌道をつくりながら公転しはじめました。
巨大な太陽の力場の中で、暗黒惑星は1000年前後の公転周期をもち、他の多くの惑星と一緒に回転していました。
そして、やがてこの太陽系に大惨事をもたらすのです。
初めの頃は生命のないこの暗黒惑星は、この太陽系からかなり離れた宇宙空間を飛びつづけていたのでした。
巨大で孤独なこの惑星は、宇宙の厳しい寒気の中を追放者として、あるいは別世界からきた異邦人のように漂流しました。
この放浪惑星は暗く危険で破壊的な惑星でした。
そして、ついにこの放浪惑星は、この太陽の広く伸びた抗しがたい力場の腕に捕えられ、一〇〇〇年の間にこの太陽系の本来の勢力圏に次第に接近し、ますます飛行速度が増大していったのです。
放浪惑星の軌道は知らず知らずのうちに狭くなり、年々他の惑星に対して危険な距離に近づいていきました。
一〇〇〇年後、この放浪惑星はものすごい速さで、突然この太陽系の中心に近い惑星軌道に入ったのです。
まるで貪欲な怪物のように、放浪惑星は宇宙の暗黒から姿を現わしたのです。それは破壊の前兆でした。
===
住民の三分の二を滅ぼした
「大接近」
放浪惑星は猛烈なスピードでいちばん外側の惑星に接近した。
この「破壊者」は太陽光線に照らされて球体としての姿をはっきり現わし、微粒子からできている微細なベールをひきずっていた。
破壊者がこの太陽系の第六惑星の楕円軌道に侵入し、数十万キロメートルの距離に達したとき、巨大な宇宙嵐が発生し、人間が建設した平和な町の大部分が壊滅した。
火山の大噴火と嵐が平和な惑星の夜を大混乱に陥れた。
山脈は崩壊し、海底の大変動が起きた。
惑星はその楕円軌道からわずかに放り出され、太陽に向かう危険な進路をとった。
===
セムヤーゼ
第六惑星は新しい軌道をさがしはじめました。
大自然の猛威に怯え、驚いた第六惑星の人々は豊かな平原(この惑星の大部分が平原でおおわれている)の上を四方に逃げまどいました。
天変地異の荒れ狂う力は、人間の助かりたいという意志力より強力でした。
この惑星の住民の三分の二は、地獄のような自然の力によって滅ばされました。
激流によって大陸の大部分が引き裂かれ、火山の爆発により広大な平地が灼熱の溶岩の下に埋没し、廃墟と化したのです。
===
第六惑星の自転周期が二倍に伸び、それまでと逆方向に自転しはじめた。
生存者はあらゆる文化を失い、惑星が誕生した当時の原始時代のように、何もかも最初からやり直さなければならなかった。
次に破壊者は第五感星の軌道を横断したが、その世界にはまさに最初の生命が誕生しようとしていた。
幸いにも破壊者はその惑星からはかなり遠い距離を通過しためで、生命の誕生の時間にはその惑星に損害を与えなかった。
====
セムヤーゼ
第四惑星では世界大戦が起こり破局に向かっていました。この第四惑星は、一番小さな惑星として自己の軌道を静かに回っていました。
予測によれば破壊者の軌道と交差する、つまり、正面衝突することになっていました。
予測どおりに事が起こったのです。
破壊者の恐るべき破壊力を避けることはできませんでした。
二頭の狂った怪物のように二つの惑星が、巨人と小人のようにものすごい勢いでお互いに突進してきました。
二つの惑星が衝突する直前に、小さな惑星に大爆発が起こり、生命を全滅させたのです。
この最小惑星の残骸は、宇宙空間の広い範囲に四散しました。
これらは流星となり、他の惑星の引力に捕えられ、その大気中で燃え尽きて消滅したのです。
最小惑星の一部は太陽に引き寄せられ、微粒子化しました。
他の一部は破壊者に引き寄せられて、その一部になりました。
===
月を捕えた当時、
地球は第二惑星だった
この太陽系の第六惑星、第 四惑星には、人類がすでに住んで、文明を築いていたという。
「破壊者」と正面衝突をし、崩壊した第四惑星の残骸の半分がどのような運命をたどったのか、セムヤーゼの説明を聞こう。
===
セムヤーゼ
まるで巨大な握り拳で投げ飛ばされたかのごとく、最小惑星の残った半分は、広大な宇宙空間を弾丸のように疾走し、遠い目標に向かって前進しました。
半分になった最小惑星は、太陽と惑星の勢力圏に何度も捕えられ、流星と衝突していくうちに形が徐々に変化しました。
数百年後、この半分になった最小惑星は表面のごつごつした円形になりました。
この小天体は荒涼とした不毛の世界であり、巨大な深い火目が散在L、生命の存在には不適でした。
この小天体は、さまざまな太陽系の力によって徐々にその速度か減ぜられ、何度も航路を変え、あるときその中の一つの太陽系(注・われわれの太陽系)に引き寄せられ、その勢力圏に入っていきました。
暗黒の死の惑星として、この小天体は外輪の惑星を通過しましたが、その際それらの惑星に何らの損害も与えませんでした。
太陽系の内輪に入ると、小天体はすでに破壊されたいくつかの惑星の断片と衝突し、大きな火口をつくりました。その結果、小天体の航路はさらにわずかながら変化し、す
でに原始的生命が芽生えていた第二惑星の軌道に平行して航行することになりました。
この第二惑星は、大きな海が多く、原始林が密生し、危険で無慈悲で驚異に満ちた原始世界でした。
この時点から三十四日経過したとき、小天体は第二惑星に追いつき、その軌道に捕えられたのです。
第二惑星すなわち地球は、この小天体を引きとめて、新しい衛星として自己の周りを回転させる力を十分にもっていました(その当時第二惑星の楕円軌道はたえず変化していました)。
それ以来、小天体は地球の周りを月として回転しているのです。
この月、すなわち小天体は、母星の地球より四五〇万年古いのです。
===
ここには驚くべき二つの事実が示されている。
一つは私たちの月が、遠く離れた恒星系から飛来したその惑星の断片であったこと、もう一つは、当時、地球は水星につぐ第二惑星であったということである。
このようなことは、現代の惑星科学の範躊で納得のいくことなのであろうか。
地球科学は、月の成因の「謎」を解いていない
月の成因については謎が多い。
地球の月は太陽系の他の惑星とたいへんに違うところがある。
つまり月は直径で地球の四分の一、質量比でいえば地球の八〇分の一と、衛星としては非常に大きい。
他の惑星と衛星のこの比はずっと小さいのである。
アイザック・アシモフは、せいぜい直径が四十八キロ(いまの月は三四七六キ口)程度が自然だといっている。
このため、月は特殊な衛星だとみられている。
月の誕生についての仮説には、まず分裂説(親子説)がある。
今より速く自転している地球から周辺部分が遠心力で飛び出し月になったとする説だが、最大の弱点は、分裂するほどの高速自転をしていたことが証明できないこと。
また月の平均密度が三・三(グラム/立方センチメートル)であるのに地球が五・五と異なっていることから不合格だろう。
集積説(兄弟説)は、原始太陽を回るチリや微惑星の中から隣りどうしの兄弟惑星が一緒に成長した。
最終的に地球のほうが大きくなり、力の弱い月が地球を回るようになったというもの。
これも月と地球の平均密度のちがいから成り立たないとされている。
捕獲説(他人説)は別のところからやってきた小型の惑星か巨大な限石が、地球に近づいたときにブレーキがかかり、運動エネルギーをなくして地球につかまったとする説。
万に一つもあるかどうかというタイミングの問題があるが、それでもこの説の支持者は多い。
人工衛星説もある。
これにはいろいろの理由があるようだが、月と太陽の直径比が四〇〇分の一、地球と月、地球と太陽の間の距離の比がほば四〇〇分の一で、太陽と月は地球からほぼ同じ大きさにみえ、皆既日食はそのために起こる。
こんな偶然があるだろうか、という疑問などから発している。こんな説が生まれること自体、月の成因が謎につつまれていることを表わしている。
「月の起源は
地球重力圏に捕獲された惑星」
アポロ宇宙船が月に行くまでと、行った後では、月に関する考え方は大きく変わってしまった。
月の岩石の分析で、岩石中の珪酸成分比が地球の石と月の石と限石では大きく違っていることがわかってきた。
また、放射性同位元素による石の年代計測によフて、月の石は三十五~四十億年のものが多いことがわかったが、地球の石の古さは三十五億年といわれている。
また、隕石の場合は四十六億年にそろっていると報告されている。
アポロ宇宙船が月に行くまでの科学者の予想は「月のクレータは隕石によってつくられたもので、月の表面には隕石がいっぱいあって、アポロ宇宙船が月に着陸するとうずまってしまうほどになっているはずだ」とされていた。
しかし、現実は隕石ではなく、玄武岩でできていた。
このことはそれ以前に月の内部が溶けており、惑星として誕生し、その中から、軽い成分が地表に浮かんで玄武岩ができたことを証明していた。
また現在の月には地球のような磁場が観測されていない。
しかし月の石は地球の石と同じように帯磁していることがわかった。
地球のように磁場をもつ惑星の表面に溶岩が流れでて固まると岩石が帯磁するのだから、月も以前は磁場をもっていたことになる。
つまり、内部が溶けていて、ダイナモ(発電機)効果が起こるようにかなり早い自転をしていたと考えられる。
もう一つ、月の表面にころがっていた石は、月にいまは磁場も大気もないので地球の石と違って宇宙線にさらされる量が多く、表面が核反応で変質している。
この度合いによってその石がどのくらいそこにあったか推定できる。
アポロの乗員が「雨の海」と「ハドレ-谷」で拾った石は九〇〇〇万年間宇宙線にさらされていたという結果が出たが、石の年齢(三十五~四十億年)に比べてきわめて短いことになる。
月の年齢の大半の期間は月に大気があり磁場があって、宇宙線を防いでいたのではないかと推定される。
こうしたデータは、すべて、月は大気をもち文明すら存在していた惑星に起源をもつという、セムヤーゼの話を裏づけているように筆者には思える。
「月の起源は惑星で、地球重力圏に捕獲された」とする衝撃的な論文が、一九八四年五月、林忠四郎京大名誉教授と中沢清東大理学部教授によって日本地球電気磁気学会で発表された。
コンピュータを駆使してまとめられたこの説は、地球の原始大気が小天体の公転にブレーキをかけたという。
従来の説に比べて矛盾点が少なく、世界の宇宙科学界でも多くの支持を集めた。
ただし、二氏がいう月は、金星と地球の間で太陽系の形成時期に同じように生まれた惑星であり、のちに地球に捕獲されたというものだが、たまたまある惑星が地球に近づいたということがありうるなら、それがセムヤーゼの説明にあるような惑星であってもよいのではないだろうか。
放浪惑星は彗星として輝きだした!
月を地球につれてきた「破壊者」放浪惑星は、はじめから「彗星」であったのではない。
月のもととなった第二の太陽系の第四惑星を破壊したのち、別な太陽系で猛威をふるい、突然、彗星として輝きだした。
===
セムヤーゼ
自己の進路に入るものをすべて破壊していく破壊者は、ある太陽に一番近い惑星をその太陽に逆らってものすごい力で追いだしたのです。
この惑星は、太陽から一〇〇万倍の距離の地点て大爆発を起こし、自壊しました。
そしてその破片は太陽に捕えられ微粒子になりました。
破壊者の軌道は元の位置からわずかにそれて、太陽に異常接近して、それから広い宇宙へ帰っていきました。
想像を絶する太陽の炎熱が放浪惑星の表面を溶解しました。そのために、猛烈なスピードのために赤熱した物質と粒子が、放浪惑星の背後に一〇万キロメートルの距離にも及ぶ長い尾をつくりました。放浪惑星本体も同様に輝きました。
こうして放浪惑星は危険な彗星に変わったのです。
宇宙の零度の冷気によって彗星の表面は急速に凝固し、元の固さに戻りました。
彗星の本体の照度は、その明るい尾とまったく同じでした。
凝固以来きわめて微細な物質と粒子が本体を覆い、それらはますます増加し、ますます長く明るい尾をつけるようになりました。
====
やがてこの彗星はわれわれのゾル太陽系に侵入し、いまは一定の周期をもってそれを周回‥する軌道におさまった。
地球に接近したうちの何回かは、天変地異を引き起こした。
年代順に並べてみると、
一万七九年前…ノアの大洪水
七九五七年前…第二の大洪水
六九〇六年前…大災変
三四五三年前…
サントリン島の大異変
これらの時期以外は幸いにか、この彗星による惨事は起こっていないという。
公転周期が変化する奇妙な彗星
それではこの彗星の公転周期は、どんな特徴をもっているのだろうか。
===
セムヤーゼ
それは私たちにとっても難問なのです。
若干の関心事は、特に絶えず変化する彗星の恒常速度ですが、それがどのようにして起こるかです。
彗星の公転期は、五七五・五年の恒常年数を経たのち、再び戻ってきます。
その間二〇三年の大きなズレが生じるとしてもです。
すなわち、彗星は期間中さまざまな惑星の太陽、また彗星自体との互いの引力によって、その全公転期に四七八年から六八三年の違いが生じるのです。
この浮き沈みする公転期が過ぎると、再び彗星は五七五・五年という恒常年数を取り戻します。
その年数は私たちにも謎で、私たちの精通した比較年数とは決していえません。
私たちの科学者は、この現象は最も不規則な間隔で起こり、この破壊者は五七五・五年の公転期が過ぎると、再び地球との危険距離に迫り、大抵は強力な破壊を引き起こすと考えられると言っています。
私たちの科学的研究によると、この独特な現象は、ゾル太陽系の逃走速度(惑星、月などの引力を克服するために、天体がもっている速度)が決定的な役割を果たしています。
ゾル太陽系は、高い速度でヘラクレス座に位置しています。
しかし、これが唯一の要因ではありません。
さらに計算と研究が行なわれた結果、ゾル系の太陽系(惑星系)も、この独特で絶えず繰り返し訪れる破壊者の公転に、決定的な影響をなしていることがわかっています。
===
ここに述べられている彗星の運行の特徴(周期が四七八年から六八三年と二〇五年のズレをもって変化するが、二度の公転期を足すと必ず五七五・五年の二倍、一一五一年で回帰する)は私たちに知られている他の彗星とはずいぶん異なる。
この公転周期の変化はあまり不規則で宇宙人にも不可解であるとされている。
宇宙人にも全体的な影響の計算ができていないことが示されている。
もちろん天文学の常識では、彗星の動きが他の惑星などに影響されて複雑になることは知られている。
しかし二度の公転期の和が必ず一定であるというような動きは知られていない。
金星は天王星の衛星だった!
巨大彗星はノアの洪水を起こしたのち、何回も回帰して(西暦一九七五年の)七九五七年前には第二の大洪水に地球を襲わせた。
その後六九〇六年前にも災変をもたらしたが、三四五三年前、彗星はその引力によって、天王星の衛星であった金星を今日ある軌道に駆逐し、そのときギリシアのサントリン島に大異変を引き起こした。
===
セムヤーゼ
金星は、破壊者の引力と天王星の太陽系(注・惑星系)によるさまざまな別の要因とから引き離され、のちに破壊者の軌道に運行しました。
いわゆる引きずり込まれたのです。
巨大彗星の速度は非常に早く、それに付随する惑星をずっと後に追いぬきます。金星が天王星の太陽系からはずれるとき、その初期速度は非常にゆっくりとしていました。
これは今から約八五九〇年前に起こりました。
このときの運行では、彗星の公転年数は六三二年で、五七五・五年の恒常年数よりも五十七年も超過していました。
その原因は私たちにもまったく謎です。
金星は、その初めの太陽系から極度にゆっくりと長円形の軌道に移りました。
そして別の太陽系(惑星系)の中に危険な軌道をとって進んだのです。もちろん中央の太陽の周りを運行しますが。
この軌道に、金星は七九五七年前までおりました。
破壊者が再び訪れ、金星を地球の進路に引っ張ったのです。
巨大彗星自体は、地球に対して危険な距離内に入り、巨大な破壊と洪水を起こしました。
これは過去一万二〇〇〇年における二度目の大洪水で、破壊者によって引き起こされたものです。
のちの経過のとき、破壊者は再び五七五・五年の恒常年数をもっていました。すなわち、六九〇六年前のことになります。
金星は再びその軌道の虜になり進路を変えたのです。
しかしながらそのときの金星は、地球に近い太陽の周囲を公転する軌道に入った程度のものでした。
金星はそこで四〇五八年前までとどまり、次の巨大彗星の経過時に、再び金星の軌道は変化させられたのでした。
金星は今までのコースからはずれ、ゆっくりと確実に地球に向かう軌道に滑り込んだのです。
それは事実起きたのです。
三五八三年前に、確実に金星はゆっくりとした軌道をとりました。
それは破壊者の再出現がなくても、地球に近づいたでしょう。
===
サントリン大異変も
彗星が引き起こした!
===
セムヤーゼ
それから三四五三年前に再び破壊者がやって来ました。
それはわずか一〇万キ口足らずの間隔で、常に軌道からはずれた諸惑星のそばを通過し、最後に金星を今の軌道に引きずり込みました。
それにより金星は、最終的には地球まで来ざるを得なくなりました。
しばらくして破壊者は地球のそばを通過し、金星はそれに引きずり込まれて、かなり地球の近くまで迫って来たため、サントリン大異変が起きたのでした。
地球のそばを通過したあとが、今日ある金星の公転軌道への始まりとなったのです。
それ以来この破壊者は何回も公転期を加え、非常に変わった公転期間を示しましたが、その後、もはやゾル系は巻き添えを食うことはありませんでした。
小さな不規則な影響はみられましたが。
こうして、破壊者は一六八〇年に再び五七五・五年の恒常年数を迎えました。
そのとき、ゾル太陽系を再び通過したのですが、今回はほとんど平和な運行であり、変化は起きませんでした。
そのことから、次の経過は五七五・五年を換算するなら、西暦二二五五年に再び破壊者が出現することになります。
===
地球物理学者竹内均氏は、著書『アトランティスの発見』のなかで、エジプト年代記と炭素14法から、エーゲ海にあるサントリン島大爆発の時期を紀元前一四一〇年頃と記している。
氏はサントリン異変をアトランティスの沈没と比定するが、その大爆発の規模を広島型原爆の一〇〇万個分、ビキニ水爆の1000個分と推定し、これまで地球上に起こった最大級の天変地異の一つだといえるとしている。
このとき発生した津波の高さは二〇〇メートルにも達し、地中海沿岸に大きな被害を及ぼしたことや、噴火による気象への影響は大きく、日射量が低下して小氷期を起こしたと推定されている。
この爆発の発生時期は六十~七十年の違いでセムヤーゼの話と一致しており、歴史的事実でもあり、興味深い。
「惑星の移植」現象は事実だったのか?
宇宙人が、金星は初め天王星の衛星軌道にあり、彗星によって今の太陽の第二惑星軌道に「移植」されたという点について検討してみよう。
惑星は太陽から近い順に水星、地球、火星……であり、かかし金星は存在しなかったのだろうか。
金星については厚い雲に覆われその表面が見えないという不可解さだけでなく、歴史的にいろいろな疑問がある。
ヴェリコフスキーは、「西暦前二〇〇〇年から一五〇〇年の間に金星が誕生した」と断言している。
彼が挙げる証拠は、西暦前三一〇三年とみられる古代ヒンズーの惑星表には目で見られる惑星のなかに金星だけが入っていないこと、古代バラモン(インド)も五惑星を知らず四惑星大系たったこと、バビロニアの天文学もまた四惑星大系で、古代の祈りのなかで呼びかけられるのは土星、木星、火星、水星の四つであったことなどである。
彼らが空に、あんなに明るい金星を見なかったということは、惑星の中に金星がいなかった、としないと不可解である。
後代になると「金星は『大きな星たちに加わった大きな星』という名称がついている」という。
大きな星たちというのは四惑星で、金星は第五の惑星となったのである。ヴェリコフスキーはほかにもいろいろと伝説などの調査もして、金星は西暦前一五〇〇年ごろに空前の大異変を地球に与えるとともに「移植」されたと結論づけている。
天王星と金星との「特殊性」にも着目しておく必要があるだろう。
ゾル太陽系(私たちの太陽系)の惑星の中で天王星は変わり者である。
他の惑星は自転の回転軸(コマの軸)が公転軌道面に対して上下に立った形で回転しているが、天王星だけは公転軌道面に倒れた形で自転しているし、衛星も倒れた軸の周りに回っている。
彗星が接近した場合、衛星が引きはがされやすい状況にあるといえるかもしれない。
セムヤーゼの説明によると金星は何回かの彗星の通過によって地球に近い軌道に外側から近づき、最後に地球に相当に接近しか位置を通過して現在の軌道に落ちついたという。
地球と月の関係を例にとると、月は地球の潮汐力によっていつも同じ面を地球に向けて公転している。
このことは、月が地球に捕えられたときにできた関係であり、仮に同じような星雲が集積してできたものであれば、最初のガスの回転成分が残り、現在のような状況は起こりえないものである。
では、地球と金星の大接近遭遇で何か起こっていないであろうか。
地球と金星が太陽からみて同じ方向に並ぶ「合」という状態があるが、そのときに、金星は地球につねに同じ面しかみせない関係になっており、地球と月の状況に似ている。
これも一種の潮汐力である。
この場合本来ならば質量が地球よりはるかに大きい太陽の影響を受けるのが当然と思われるが、地球の影響を強く受けていることは、地球と金星の大接近による、金星の自転への地球からのブレーキ作用があったと考えてよいだろう。
このせいかどうかは明らかではないが、金星だけが他の惑星と逆方向(天王星は除く)に自転をしているし、地球時間で二二五日の公転に対して、自転が二四三日に一回であり、金星の一年は金星の二日である。
さて、これまでわれわれは、セムヤーゼが描写した宇宙的な規模の天変地異が、現代の惑星科学の常識でどこまで検証できるかということに留意しながら、宇宙人の語る「創世記」の物語を紹介しようと努めてきた。
そこでは宇宙を放浪する「巨大彗星」が大きな役割を演じていたが、宇宙人によって次に述べられる人類発祥の歴史、その隠された秘密を理解するうえでも、この彗星の存在は非常に大きなウェイトを占めているのである。
(以下、省略)
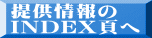 |